バスに乗る皆さんが必ず見るもの、それは方向幕ではないでしょうか。この方向幕を見ることで皆さんは行き先を知り、自分が行きたいところに行くバスに乗ることかと思います(無論、全ての人がそうだとは限りませんが)。ここでは、そのバスの方向幕について考察してみましょう。対象はもちろん、横浜市営バスです。
ここでは、いくつかのトピックに分けて解説していきます。
市営バスの第1号車(A型フォード:当然アメリカ製)から方向幕は備え付けられていました。古いバスのイラストを見ると、後方にも方向幕用の窓があるようですので、後方にも方向幕があったのかもしれません。ちなみに側面はプレート状のものだったようです。
同様に古い写真を見ると、開業当時の車両の方向幕には日本語の表記の他に英文字も併記されていたようです。
ちなみに、そのころの市電の方向幕はバスと同様日本語と英文字の併記だったようですが、その他に方向別による地の色の色分けも行われていたそうです。どういうことかというと、例えば桜木町の駅から横浜公園、桜道下(現在の麦田町)、本牧方面へ行く電車の方向幕の地の色は青、弘明寺、磯子方面へ行く電車は白地、神奈川方面は行く電車は赤地というものだったそうです。バスのページではありますが、もうちょっとこの話を続けましょう。こうすることで、まずは接近してくる電車の行き先の方角が分かるわけです。そしてその電車が近づいてきて字数や系統番号表示などで実際の行き先がわかるという仕組みです。夜間などは効果的だったようです。現在、最終バスは赤い色の「終車灯」を方向幕につけて走りますが、これは上記の方向別の行き先表示が元になっているそうです。
この方向による色分けは終戦まで続きました。
さて、話をバスに戻しましょう。戦後になって系統番号がきちんと設定されるようになりました。
戦後まもない頃のバスには系統番号の設定はあったものの、系統番号を表示しているバスの写真が(今のところですが)見あたりません。昭和30年代になって導入されるようになったバス(ボンネットバスではなくてリアエンジンタイプのバス)あたりから系統番号表示窓がついたバスが導入されているようです。その表示窓は路面電車の系統番号表示と同じように正面から見て右側中央部あたりに設置されていたようです(古い写真から)。
その後、昭和39年頃の車両は前面の行き先方向幕部に系統番号と行き先を併記する形式で表示するタイプ(早い話、現在の方向幕と同じスタイルです)になったようです。
ちなみに、現在では当たり前ですが原則として(1975年度車まで)後部には方向幕の設置はありませんでした。初期は現在のように電動式ではなく、手動で方向幕を切り替える必要があり、車掌さんがいれば車掌さんにやってもらえるわけですが、ワンマン運転などの際は大変だということで設置されなかったのかなと思われます。
昭和40年代になり、市電の廃止やら路線の増強などで方向幕を増やす必要ができてきたのか系統番号部と行き先部を分ける方式になりました。そして方向幕自体の電動化も進んできました。なお、1975年度車までのバスの方向幕は布製の方向幕で、切り替えについてもボタンを押している間だけモーターが作動するタイプだったため、定位置で方向幕を止めるのはなかなか難しかったようです(その後は1回押すと1幕分動くようなタイプになりました)。
1976年度車から後部にも方向幕が設置されるようになりました。後方からも行き先が確認できるようになったため、利便性はかなり向上したかと思われます。ちなみに、それ以前からページ作者の母方の実家のある吉祥寺周辺を走る関東バスには後部方向幕が設置されており、市営バスで後部に方向幕のある車両を発見したときは「市営バスも関東バスと同じようになったんだ!!」と思ったものでした(当時5歳でした)。
この年代の車両から方向幕に使用するものが布からビニール系のものに変更されました。なお、布から変わった新しい材質のこの方向幕ですが、静電気の発生が多くなり、方向幕を動かす装置周辺につく塵や埃などが方向幕本体についてしまうという副作用を起こすようになりました。現在でも、方向幕をしばらく使用していると方向幕が汚れてしまう現象がよく発生します。
1982年度になると、今度は大型の方向幕が採用されるようになりました。前後面、側面ともこれまでの幕と比べて約2倍の大きさとなり、より見やすいものになりました。この方向幕については後ほど詳細を書いていこうと思います。こうして、現在に至っています。以下、私が知る方向幕について多少踏み込んで話をしていきましょう。
私が生まれた時点ではまだ後部に方向幕はありませんでした。ですから、例えばいすゞの1973年度車から1975年度車の後部などは屋根のところまで窓ガラスが続くという独特のスタイルをしていたものです。
先に書いたとおり、その当時の方向幕は布製で、系統番号部と行き先表示部とが別々の幕になっていました。ですから起終点にて方向幕を変える場合、同じ系統で折返しを行うのであれば方向幕のみを変えればよい理屈となっていました(現在の緑営業所の一部の方向幕と同じ理屈です)。
系統番号表示部イメージ
| 37 |
| 20 |
| 26 |
| 36 |
| 44 |
| 96 |
| 68 |
以下
続く |
行き先表示部イメージ
| 横 浜 駅 |
| 県庁前 山 手 駅 |
| 海岸通 横 浜 駅 |
| 海岸通 本牧市民公園 |
| 海岸通本 牧 車 庫 |
| 海岸通 海づり桟橋 |
| 海岸通本 牧 ふ 頭 |
| 海岸通山 下 ふ 頭 |
| 以下続く |
これらを組み合わせて表示させていました。
| 1975年度車の方向幕の例 |
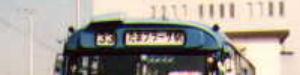 |
1986年11月:中山駅北口にて撮影
(この写真は拡大できません) |
|
そして、1976年度車から方向幕は後部にも設置されるようになりました。また、この年代の車両から方向幕の動作タイミングが1回押すごとに1幕動くというスタイルとなりました。
さて、それまでの方向幕は系統番号部と行き先表示部が別々の幕になっていましたが、この1976年度車から正面から見る限りでは系統番号部と行き先表示部で別れているものの実際には一体化されました。系統番号部と行き先表示部の境目のところには運転席側から見えるような幕番号が振られており、方向幕を動かす際の目安となっていました。
1976年度以降の車両の方向幕イメージ
| 105 51 市 庁 前 横 浜 駅 |
| 105 52 市 庁 前 花 咲 橋 |
| 105 53 市 庁 前 |
| 105 54 大鳥中学校本牧市民公園 |
| 105 55 大鳥中学校本牧車庫 |
| (以下続く)) |
なお、51や52等の番号は実際には運転台から見られるように表裏が逆になっています。
こうして1981年度までの5年間はこのスタイルで続きました。なお、この方向幕のスタイルは晩年(?)は表示スタイルが大型方向幕車とあわせるような形になり、経由地の表示のない幕が多くなっていました。
1982年、この年から方向幕が大型化されました。先に書いたとおりこれまでの方向幕に比べて2倍の大きさになりました。しかし、これの実施には思わぬ落とし穴がありました。
大型方向幕の場合は方向幕が大きくなったために1つの幕に入る幕数が100コマ(00〜99番)しかなく、緑営業所(当時)のように方向幕数が多い(100コマを越える)営業所では系統番号と行き先表示部をそのままの状態で移行することができませんでした。その為、1975年度車までのように系統番号部と行き先表示部を分けることになりました。ちなみに、この当時は港南営業所と野庭派出所(当時)の方向幕がまだ共通化されており、幕数が多かったため港南、野庭車では1982年度車のみ系統番号部と行き先表示部が別々になっていました。
大型方向幕になったため、方向幕切り替え方法が変更になりました。運転席内にパネルを設置し、そのパネルで方向幕番号を設定して機械的に変更するスタイルに変更となったのです。ちなみに、系統番号表示部と行き先表示部が別れているスタイルの場合は、行き先表示部がパネルでの変更で、系統番号部は別に手動で変更するスタイルでした。この系統番号部と行き先表示部を分けるタイプで面白いのは行き先を変更している際にいろいろな表示を見ることができることです。例えば、横浜駅西口から中山駅に変更する際など、鶴見駅西口とか新横浜駅などという方向幕を見ることができたのです。
 |
↑ 39系統「八反橋」行き?
1999年4月 横浜駅西口にて撮影
(写真をクリックすると拡大されたものが出ます) |
|
大型方向幕は当初、系統番号と行き先のみの表示でした。しかし、これでは経由地がわからないため、最近では経由地表記が併記されるようになってきました。また、1992年度後期車からは英語表記も併記されるようになりました。英語表記併記はその後それよりも前の車両にも適用され、現在ではほぼ9割程度の車両が英文字表記併記となっています。
なお、英文字表記にはこんなものがあります。
英文字表記について
(共通部) |
| バス停名 |
英文字表記 |
| ○○駅(○口を含む) |
STA. |
| ○○車庫 |
SHAKO |
循環線は経由地を表示の上、終点を表記
(例) |
54産業道路本牧ふ頭循環
HONMOKU PIER - NEGISHI STA. |
| 主な英文字表記 |
| バス停名 |
系統番号 |
英文字表記 |
港湾病院 |
2系統 |
KOWAN HOSPITAL |
| みなと赤十字病院 |
2系統、58系統 |
MINATO RED CROSS HOSPITAL |
| 本牧市民公園 |
8、26、105、106系統 |
HONMOKU SHIMIN PARK |
| スカイウォーク |
17、109系統 |
SKY WALK |
| 市電保存館 |
21、78系統 |
SHIDEN HOZONKAN |
| 横浜港シンボルタワー |
26系統 |
SYMBOL TOWER |
| 京急ニュータウン |
30、45系統 |
KEIKYU NEW TOWN |
県庁前 |
32、79、89系統 |
PREFECTURAL OFFICE |
| 三ツ沢グランド |
37系統 |
MITSUZAWA GROUND |
| 瑞穂桟橋 |
46系統 |
MIZUHO PIER |
| 中央市場 |
48系統 |
CENTRAL WHOLESALE MARKET |
| 南区役所 |
60系統 |
MINAMI WARD OFFICE |
| 富岡バスターミナル |
61系統 |
TOMIOKA BUS TERMINAL |
| 造船所 |
63、70系統 |
ZOSENJO |
| 旭硝子 |
83、129系統 |
ASAHI GLASS |
| 下水処理場 |
85系統 |
GESUI SHORIJO |
| 一本松小学校 |
89系統 |
IPPONMATSU ELEMENTARY SCHOOL |
| よこはま動物園 |
5、136系統 |
YOKOHAMA ZOO ズーラシア |
|
次に、深夜バスの方向幕についてちょっと触れておきます。深夜バスについては別にページを用意しておりますので、詳しくは書きませんが、このような表示になります。
| 深夜 |
元町 |
本牧車庫
HONMOKU SHAKO |
| バス |
間門 |
これは364系統(105系統深夜バス)の方向幕です。市営バスの場合は系統番号は表示されません。深夜バス独自の系統が多いせいからでしょうか?
最近では、場所によっては青色の文字で表記(新横浜駅、パシフィコ横浜など)される方向幕があります。
ここでは、最近見られる電工式、液晶式(こちらは無くなってしまいました)の方向幕について紹介したいと思います。
4−1.電光式方向表示(LED式方向表示機)について
2002年度(以降)車と浅間町営業所の9−3671号車、9−3672号車には電光式の方向表示機が装備されています。2005年3月までは本牧営業所の5−2519号車、5−2522号車にも別の電光式方向表示機が取り付けられていましたが、現在は幕式に戻されています。
最初に、現在は見られなくなってしまいましたが本牧営業所に最初に導入された方向表示機を見ていきます。
電光表示車の前後面
(本牧営業所1995年度車) |
 |
 |
↑ 2枚とも2002年7月:根岸駅にて撮影
(写真をクリックすると拡大されたものが出ます) |
|
この表示機はなかなか優れもので、車内放送装置などと連動して経由地表記などを変更することができます。106系統本牧車庫発境木中学校行きを例に見てみましょう。
まず、本牧車庫出発時はこの表示になります。
| 106 |
境木中学校 |
| 元町 |
SAKAIGI JR. HIGH SCHOOL |
次に、元町のバス停を案内する放送が始まると方向幕の経由地が変わります。
| 106 |
境木中学校 |
| 戸部駅 |
SAKAIGI JR. HIGH SCHOOL |
経由地が戸部駅になりました。そして、戸部駅の放送が始まると今度は経由地表記がなくなります。
| 106 |
境木中学校 |
| SAKAIGI JR. HIGH SCHOOL |
そして境木中学校に向かうのです。なお、後部は幅がないため、経由地表記は系統番号と行先表示の間に入ります。
では、この車両が終バスに入るときの表示を紹介します。終バスは一般的には赤い色のランプの終車灯を方向幕に点灯させますが、この場合は以下のようになります。
| 106 |
境木中学校 |
| 元町 |
SAKAIGI JR. HIGH SCHOOL |
|
上図の通り終バスに入る場合は表示の周囲に赤いランプが表示されます。
終バスの時の写真を以下に紹介します(2000,09,17)
| 終バス運行時の前後面 |
 |
↑ (2003,−4,13:差し替え)
2001年5月:撮影
(写真をクリックすると拡大されたものが出ます) |
 |
↑ 2000年9月:撮影
(写真をクリックすると拡大されたものが出ます) |
|
それでは、深夜バスはどうでしょうか?深夜バスはこうなります。
深夜
バス |
元町 |
本牧車庫 |
| HONMOKU SYAKO |
|
終バスでは赤色になるところが緑色になります。なお、これは105系統の深夜バスです。経由地は最初は元町になっていますが、元町の放送が流れると間門に変化します。また、後部方向幕は「深夜」のみ表示されます。
(2003,−1,−3:写真追加、情報一部変更)
| 深夜バス運行時の前後面 |
 |
↑ 2002年12月:撮影
(写真をクリックすると拡大されたものが出ます) |
|
側面の表示は以下のようになります。
| 電光表示車の側面 |
 |
↑ 1999年5月:桜木町駅にて撮影
(写真をクリックすると拡大されたものが出ます) |
|
この電光式方向表示機ですが、メンテナンスフリーであり系統の変更などにも柔軟に対応できるのですが、昼間などはあまりはっきり見ることができないのが欠点かと思われます。
なお、2002年度の新車からLED方式の方向表示機が正式採用となりました。2001年12月頃、浅間町営業所の2台を使用して新しい(本牧車のものとはメーカー、仕様が異なります)LED方式のテストが行われ、2002年8月導入の新車から正式に採用となりました。
こちらのタイプの表示は下のようになります(以下の図は多少実際とは異なりますが、イメージとしてご覧ください)。
|
元町・マイカル本牧 |
|
|
本 牧 車 庫 |
|
HONMOKU SHAKO |
ちなみに、経由地表記には柔軟性(?)があるようで、
のように、行先表示と並列に表示することも出来ますし、下のように
経由地表記がない行先表示も表示可能なようです。
新しいタイプのLED表示車
車両はいずれも9−3671(浅間町)
(拡大は出来ません) |
 |
 |
 |
|
側面の表示は上記3枚目の写真にあるとおりです。上部の系統番号、経由地・行先表示はバス停停車時にはスクロール表示を行います(日本語の表示と英語の表示が交互に表示されます)。
(2005,−5,−8:追記)
緑営業所の2002年度車の後部表示では当初、西菅田団地経由東神奈川駅西口行の表示がうまく表示できず、経由地表示が「西菅田団」となっていました。現在は「西菅田団地」と表示されるようになっています。
緑営業所車の後部表示の変遷
(拡大は出来ません) |
 |
導入当初
(2002年11月) |
 |
(2005年5月) |
|
(2003,−1,−3:追記)
こちらのタイプでも終バス、深夜バスの表示は本牧営業所に最初に投入されたタイプのものと同じになることがわかりました。側面については側面に「終車」の文字が表示され、赤いランプが2つ点灯します。このページでの写真が多くなったので写真は別ページに掲載します。
本牧営業所に2002年度投入された車両については最初にLED式方向表示機が設置された車両と同じように指定された経由地を越えると経由地表記が変わったり、経由地表記が消えるたりするようになっていました。これは側面についても行われているようで、表示が切り替わるようになっていますまた、26系統については平日と土休日で経由地表記を変えています(2004年2月に解消)。これらについては以下で紹介しております(2004,−8,28:127系統を追加、26系統の記述変更、写真1枚差し替え)。
(2005,−5,−8:追記)
LED式方向表示機の表示が途中で変わる例は当初本牧営業所の車両で見られましたが、現在では他の営業所の車両でも見ることが出来ます(NT(302系統)、緑(41系統)、浅間町(127系統)など)。
最後に、上記以外でのLED式方向表示機表示例をいくつか集めてみました。こちら(2003,−4,13:ページ追加)をご覧下さい。
4−2.液晶式方向表示について
液晶式方向表示車は鶴見営業所で2台が改造されました。8−1314号車と8−1318号車です。こちらについては既に廃車になってしまっていることと、この車両に乗ったことがなかったため簡単に紹介していきます。
この車両の方向幕表示の特徴は漢字表示と英語表示が交互に出現するというところです。まず、
と、表示されます。しばらくするとこれが英文字表示になるのです。
ちなみに、漢字表示部はだいたい5文字分であり、4文字の場合は左詰めに表示されます。2文字、3文字では均等割付になっていました。
この液晶式方向表示ですが、昼間だろうが夜間だろうが見にくいというのが印象としてありました。残念ながらこの方向表示は取り付けられていた車両の廃車に伴い1998年度末には見られなくなってしまいました。
